日本景観生態学会にて「社寺林の持続的保全と収益化の両立」をテーマに、循環葬®︎の取り組みを発表。
森に還る研究所の取り組みの一環として、神戸大学大学院農学研究科と共同発表
人と自然にやさしい循環葬®︎「RETURN TO NATURE」を監修するat FOREST株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:小池友紀、以下:at FOREST)は、森に還る研究所の取り組みの一環として「日本景観生態学会 第35回大会」にて、パネル発表を行いました。
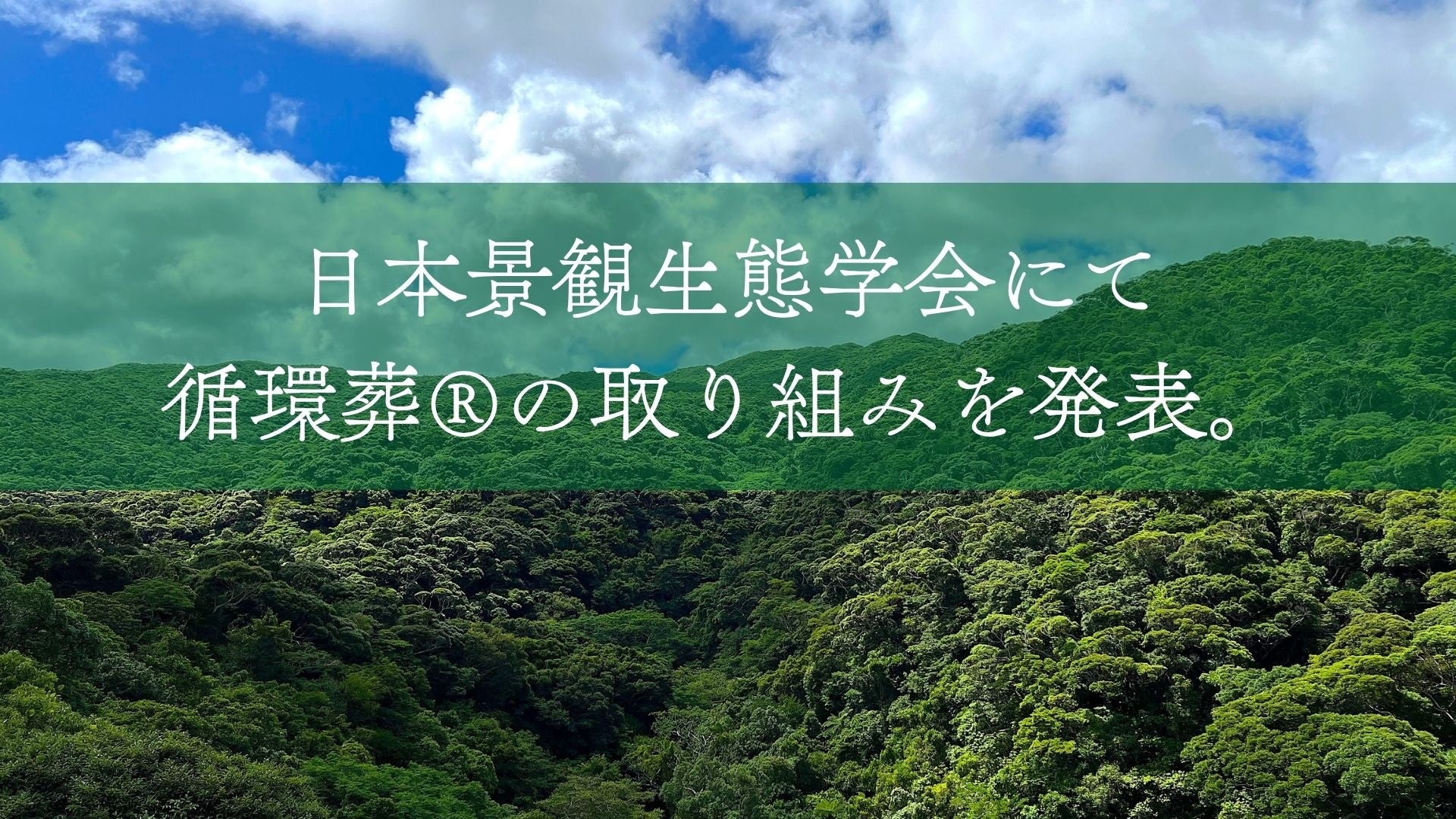
▪︎発表の背景
日本には、コンビニの数より多いとされる7万以上の寺院が存在しますが、檀家の減少や人手不足という理由から、境内にある森林の管理が行き届かず、そのまま放棄されることが増えています。循環葬®︎RETURN TO NATUREの森林アドバイザーである神戸大学 森林資源学/石井弘明教授は、放棄林を自然性の高い状態(※)で保全・管理する方法を研究しており、社寺林の問題にも取り組んでいます。循環葬®︎の取り組みが、放棄林問題における解決策のひとつと捉え、今回の共同発表に至りました。

なお、日本景観生態学会は自然の過程や風土を活かした国土・地域計画に科学的根拠を与える学問、景観生態学の進歩をはかるとともに、普及・交流を通じてその理解に努めることを目的とした学会です。
※ 在来種を調査し、元々あった自然の森に近い状態を人の手で保ちながら管理。なお、循環葬®︎では人の手を加えながらも、最終的には人の手を必要とせず自然循環する森づくりを目指しています。
▪︎研究の結果と評価
循環葬®︎では、拠点開発において事前に植生を調査し、その森に適した整備・管理を行うことを大切にしています。千葉に開設される関東初拠点では放棄されたヒノキの人工林を整備。長年手入れがされておらず、多くのヒノキが枯死しており、下草や若木が少ない単純構造となっていたヒノキ林を、自然林に再生する形で活用しています。一方で、隣接する自然のままの照葉樹林エリアでは、さまざまな種類の木が上下に重なり合い、若い木々も育つ“豊かな構造”の森が広がっていました。多様度指数(H’)はヒノキ林でH’=1.19、照葉樹林ではH’=2.74となり、ヒノキ林で見つかった広葉樹は4種類だったのに対し、照葉樹林では26種類確認されました。
こうした調査を踏まえ、管理放棄されていたヒノキ林を「埋葬エリア」として、隣接する自然の森を「憩いのエリア」として整備。訪れた方が森の中で静かに故人を偲べるよう、デッキや遊歩道を整備するとともに、ヒノキ林には必要な間伐、植樹を行い、また憩いのエリアの整備で移植が必要になった木々(計30本)は、埋葬エリアへ植え替えました。これにより、埋葬エリアの種多様度指数の向上が認められ、自然林の再生につながる結果となっています。
循環葬®︎は、誰にでもいつかは訪れる死(埋葬・供養)と森林保全という世代を超えた長期間の営みを組み合わせることで、管理放棄された社寺林を自然林へと誘導し、持続的な森林保全に必要な収益を生み出すことが期待できるという評価を得ています。今後も、石井教授とともに自然性の高い森を育て、森に新しい命の循環を生み出せるよう継続的に調査・研究を行っていきます。
「森に還る研究所」について
at FORESTは、循環葬®︎RETURN TO NATUREを運営してきた知見を生かし「森に還る研究所」を設立。自然葬がより身近になり、選びやすい選択肢となることを目指すとともに、森林埋葬が本質的に地球環境の再生につながる形で広がっていくことを目指します。世界の自然葬の潮流や地球環境への影響、埋葬や弔いに関する文化的な調査なども広く発信し、分野を超え、立場を超えて語り合う共創の場として活用し、情報発信していきます。